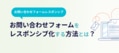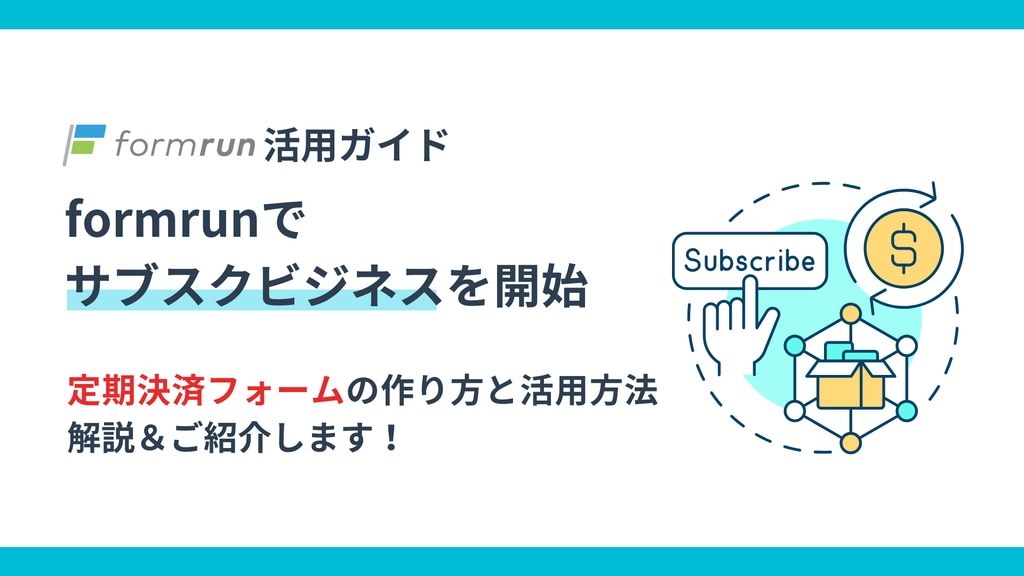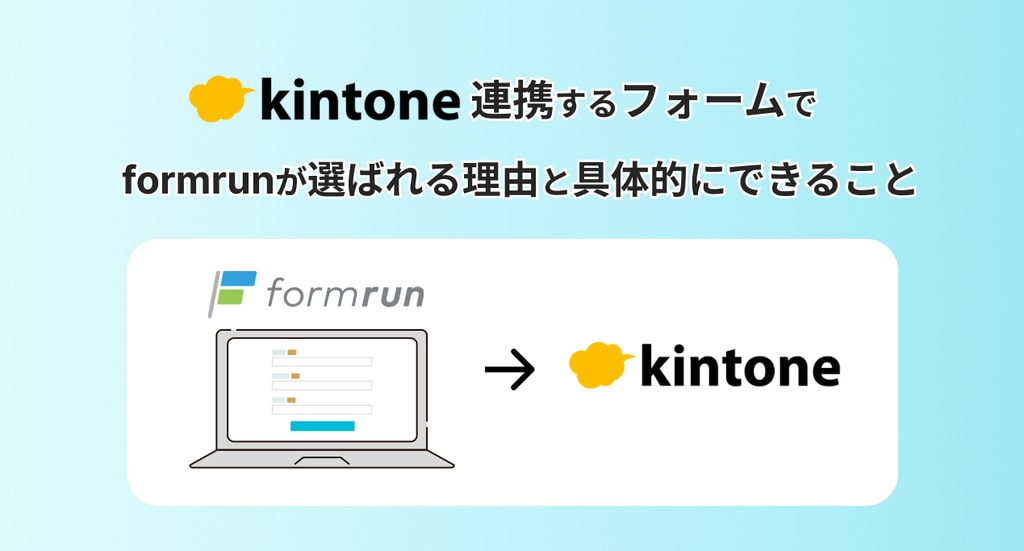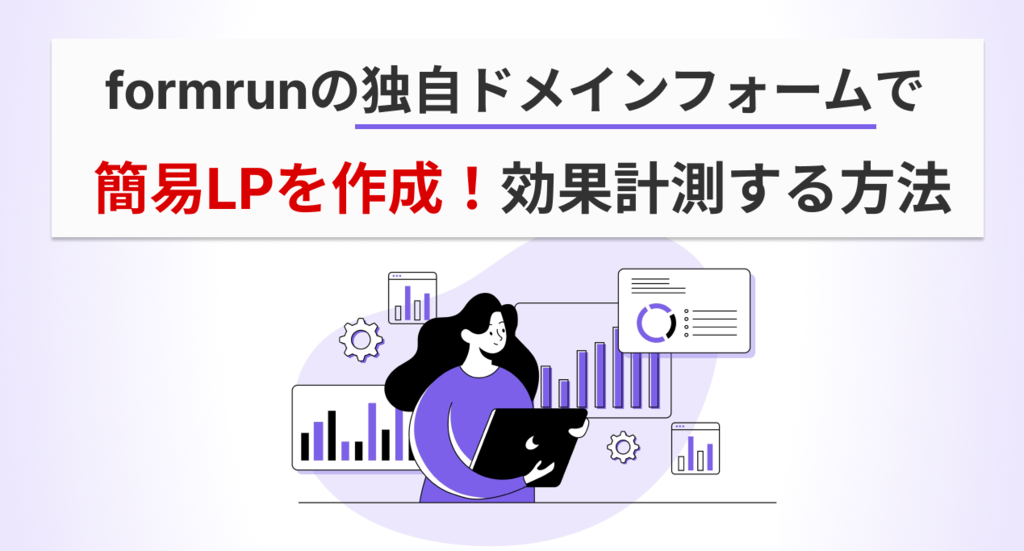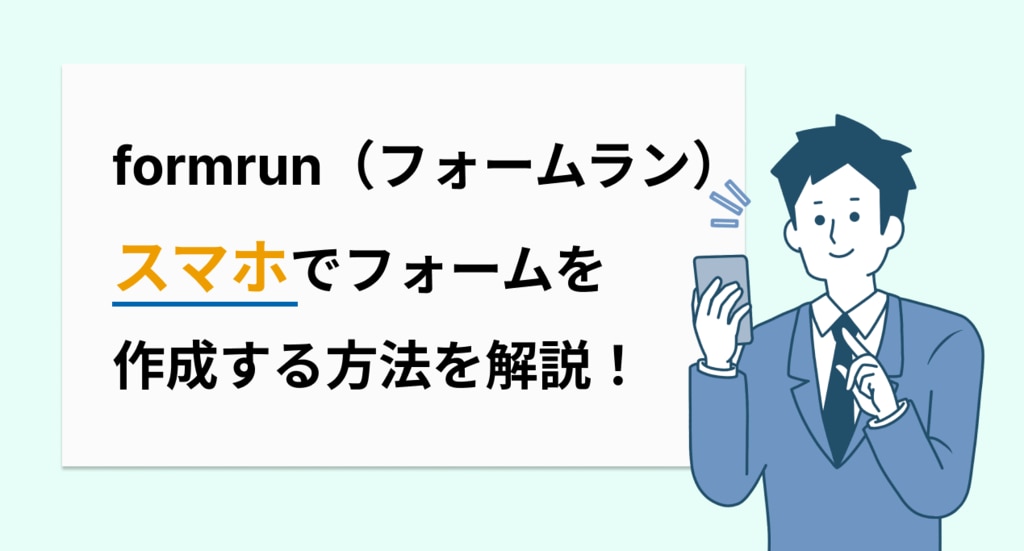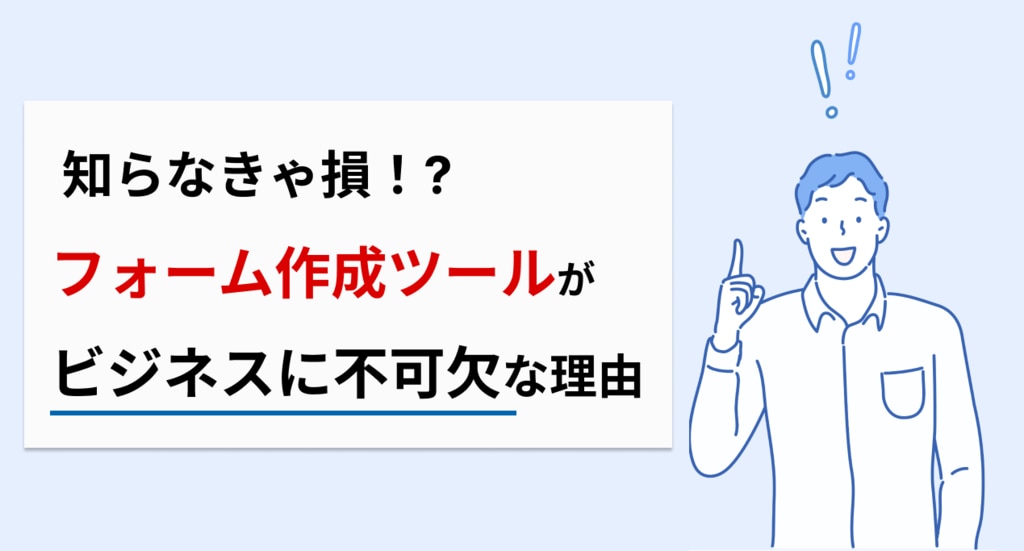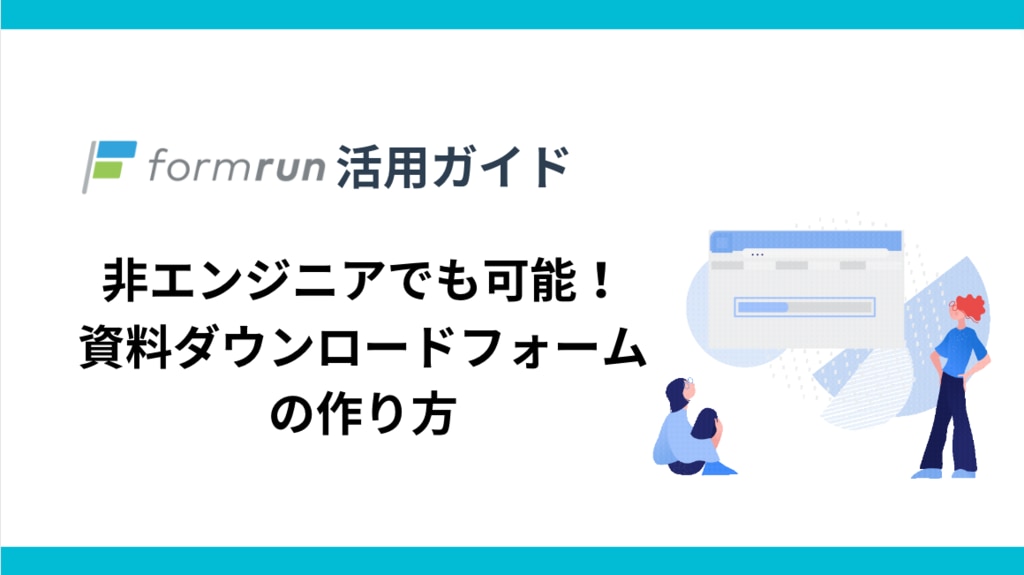問い合わせフォームを埋め込むメリットは?誰でも今すぐできる方法を解説
「うちのWebサイトには現状、問い合わせフォームが無い」
「問い合わせフォームの埋め込みをできたら良いのに」
この記事を今読んでいるあなたは、今まさにこのようなことを解決したいのではないでしょうか?
そこでこの記事では、自社Webサイトへ問い合わせフォームを埋め込む方法を解説します。
難しい作業が不要で、誰でも簡単にできる方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
簡単にフォームを共有するなら「formrun」がおすすめです。
顧客の回答の負担を少なくするEFO機能がある、外部ツールとの連携も簡単です。
目次[非表示]
問い合わせフォームをWebサイトに埋め込むメリット
企業が顧客からWeb経由で問い合わせを受ける場合、最もシンプルな方法は、企業としての代表メールアドレスをWebサイトなどに明記しておくことです。
しかし、メールアドレスを常時公開していると、迷惑メールの受信が増えてしまうなどのデメリットもあります。
メールアドレス公開よりも良い方法は、問い合わせフォームを自社Webサイト上に埋め込むことです。この方法は、企業側にも、ユーザー側にも、複数のメリットがあります。
ユーザー側のメリット
どこから問い合わせをすれば良いか分かりやすい
Webサイト上などに「お問い合わせはこちら」とメールアドレスを記載する場合よりも、ユーザーにとって、どこから問い合わせを送れば良いのか分かりやすくなります。
Webサイト上にテキストとリンクでメールアドレスを記載しても、レイアウトやフォントサイズ次第では他の要素に埋もれてしまうことがあり、誰にとっても視認性が高いとは言えません。
問い合わせフォームを埋め込んで、「お問い合わせはこちらから」など目立つ誘導ボタンを設置すれば、ユーザーは「ここから問い合わせを送れば良いんだな」と直感的に分かりやすくなります。
問い合わせアクションが一度で完結
問い合わせをする際、「氏名」「住所」「電話番号」などユーザー側が必須で明記すべき項目がケースバイケースであると思います。
しかしメールだと、ユーザー側が必要な全項目を漏れなく明記するとは限りません。
半角・全角の不統一や、電話番号や郵便番号などに関しては数字・ケタ数の入力ミスも考えられます。
入力内容が不十分だと、一旦問い合わせを送った後に企業側から再度問い直しが必要など、1件の問い合わせについて何往復も連絡を取らざるを得ない状況も出てきます。
一方、お問い合わせフォームには、ユーザーに向けて入力間違いの訂正を促す「エラーコレクト機能」を付けられます。
ユーザーの入力プロセスにおけるミスを極力防ぐことができれば、スムーズに問い合わせアクションが完結します。
問い合わせが相手先に届いたことをすぐに確認できる
問い合わせフォームには、自動返信機能を付加できる場合があります。
この機能を使えば、ユーザーが問い合わせを送信後に「受け付けました」と24時間365日、自動メッセージを返すことができます。
ユーザーは「自分の問い合わせが正しく相手先に届いたんだな」と送信直後に確認でき、安心感を得ることができます。
企業側の視点
必須項目を一度で確実に取得できる
問い合わせに付随してユーザーに必ず入力してほしい「住所」「氏名」「電話番号」など、必須入力フィールドをあらかじめ整えることができます。
ユーザー側で入力漏れがあると先に進めない仕組みにできるので、企業側にとっては、一度で確実に必要な情報を取得できるメリットがあります。
自動返信機能を使えば、問い合わせ受付が24時間365日対応に
問い合わせフォームに自動返信機能を付ければ、一次対応までは24時間365日受け付けることができます。
一次対応の自動返信メッセージでは「問い合わせを受け付けました、回答は追って担当者よりお送りします」といった案内にしておき、詳細は営業時間中に手動で返す、という方法です。
たとえ自動であっても、回答を求めているユーザーに対して何らかのメッセージを返すことができると、ユーザー側の安心感につながります。
問い合わせ内容をまとめやすい
問い合わせをeメールで受け付けている場合、「いつ」「誰から」「どんな問い合わせを受けて」「それに対して社内の誰が、いつ、どう返したか」を一元管理することが困難です。
返信担当者のメーラーを開かなければ、「いつ」「どんな返信をしたのか」追跡ができないケースも考えられます。
一方、問い合わせフォームを使えば、「受けた問い合わせ」「それに対する返答内容」が一つの管理画面に蓄積される状況に整えることもでき、一元管理がしやすくなります。
一度集めたデータを販促にも活用できる
問い合わせフォームを使えば、ユーザーの「メールアドレス」「氏名」「会社名」など顧客情報を効率的に取得できます。
ユーザーが問い合わせ内容を送信する画面内で「後日、弊社よりメルマガやDMなどご案内を送る場合があります」などと明記し、
ユーザーの許諾を取っておけば、蓄積される顧客情報をそのまま顧客基盤とし、販促に活用することができます。
迷惑メールを防げる
自社Webサイト上にメールアドレスを明記しておくと、どうしても迷惑メールの受信数が増えてしまいます。
一方、問い合わせフォームはWebサイト上に自社メールアドレスそのものを公開する訳ではないので、迷惑メールを防げるメリットがあります。
問い合わせフォーム埋め込みのさまざまな手法
自社Webサイト内に問い合わせフォームを埋め込むには、いくつかの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを解説します。
htmlで記述する
htmlを記述して、一から問い合わせフォーム画面を構築する方法です。
- メリット:入力フィールドや画面デザインなど、自社の好きなように実装できる
- デメリット:htmlの記述ができるコーダーやエンジニアの人手・時間が必要
WordPressのプラグインを利用する
自社WebサイトがWordPressを使って構築されている場合、「プラグイン」という拡張機能を使って問い合わせフォーム画面を追加できます。
- メリット:自社サイトをWordPressで構築している場合、プラグインを活用すれば比較的効率よく問い合わせフォームの実装ができる
- デメリット:プラグインの種類が膨大にあるため、「どれを選ぶのが自社にとってベストか?」と検討し、実装するための専門的な知見・技術が必要
無料の問い合わせフォームツールを利用する
htmlやWordPressの専門知識が一切不要かつ無料で、既製品の問い合わせフォームツールを利用して埋め込む方法です。
- メリット:難しい知識・技術は一切不要で、誰でも無料で問い合わせフォーム埋め込みが完結する
- デメリット:既製品なので、場合によっては自社Webサイトとデザインの親和性が低い場合もある
有料の問い合わせフォームツールを利用する
誰でも簡単に設置できる問い合わせフォームツールには、有料の製品もあります。
ややコストは掛かりますが、単に「問い合わせを受けて集約する」だけに留まらない、高度な機能を利用できます。
- メリット:単に問い合わせフォームを埋め込むだけでなく、「顧客管理機能」「外部ツール(SlackやChatWork)連携」など、より高度な機能も付いてくる
- デメリット:初期費用・運用費用が必要
ツール選びのポイント
問い合わせフォーム埋め込みに活用できるツールと言っても、無料から有料まで数多くの種類が存在しています。
ツールを選ぶ時に重視したほうが良い4つのポイントを解説します。
顧客管理機能はあるか
まずは、顧客管理機能の有無に着目しましょう。
問い合わせをしてきた顧客の氏名や連絡先情報を分かりやすく一元管理できるのはもちろんのこと、「対応ステータス(いつ、どの担当者がどんなレスポンスをしたか)」を可視化できると、複数名で対応を行う場合に抜け漏れを防止できて便利です。
それに加えて、「顧客の購入ステータス(購買履歴の有無、検討中など)」や、「趣味嗜好」なども含めてデータ管理ができると、後々フォローメールを送るなど、マーケティング活動に役立ちます。
外部ツールとの連携
社内でSlackやChatWork等のチャットツールを使っている場合、問い合わせフォームと連携できれば顧客対応のスピードアップを図れます。
例えば、顧客から問い合わせが入った時、Slackに通知が来るなどの設定ができる場合があります。
また、チャットツールに限らず、MA(マーケティングオートメーション)ツールや、SFA(営業支援)ツールと連携できるものもあります。
問い合わせフォームに対応する担当者だけが、受信日時・内容を確認できる体制ではなく、マーケティングチームや営業チームとも連携できると、顧客一人ひとりに対して常に一貫性のある返答ができるようになり、顧客体験を向上させていくことができます。
データ出力方式
データ出力とは、問い合わせフォーム経由で来た質問や顧客情報を、CSVファイルなどで一括出力することです。
顧客情報や、行動履歴をまとめて分析して、マーケティングに活かそうとするならば、データ出力機能は必須です。
ツールによっては、「データ出力は有料オプション」という場合もあるので、ツール選定時によく確認しましょう。
セキュリティ対策
顧客は問い合わせフォームに、氏名、住所、電話番号、会社名など個人情報を入力することになります。
企業として、顧客の個人情報を預かる以上は、安全に取り扱う責務が生じます。
顧客データベースへの不正アクセスなどが起きると個人情報流出に繋がり、顧客に不安を与えるだけでなく、企業としての社会的信頼度も低下してしまいます。
ツール選定時には、データ暗号化や、顧客データベースにアクセスできる権限設定などができるかどうかも確認しましょう。
マストな入力項目は?
問い合わせフォームツールを使う場合にしても、自社でコーディングを行って一から構築する場合にしても、設置前に入力項目の設計が必要です。
以下の表で示すのは、問い合わせフォームによく設置される項目例です。
これらの中から、自社の目的に応じて、必要なものを設置してください。
ただし、必須項目が多いとユーザーにとって入力の負担が生じ、途中で離脱されて問い合わせアクションが完了しない場合が考えられます。
項目は極力少なくするよう、よく精査して最低限まで絞り込みましょう。
|
また、入力エラーがあった場合、即座にエラー表示をするフォームになっているかもチェックしたいポイントです。
記入途中で入力フィールド直下にエラーメッセージが表示されれば、ユーザーはその場でエラーに気づくことができます。企業側は、必要な情報を無駄な手間を掛けずに取得できます。
ユーザーの入力負担を下げなければ成果は出ない
問い合わせフォームをこれから自社Webサイト内に埋め込むなら、とにかく「ユーザーの入力負担を下げること」を重視しましょう。
問い合わせフォームを設置する目的は、「できる限り多くのコンバージョン(CV)を獲得する」ことであるはずです。
コンバージョンとは、ビジネスの成果のことです。企業によってその定義は若干変わりますが、例えば「商品・サービスに関する新規問い合わせ」「資料請求」「来店予約」などユーザーからのアクションを獲得することです。
問い合わせフォームを新規で設計する前に、「自社が追求したいコンバージョンとは?」とユーザー視点に立って徹底的に考えてみましょう。
そして「コンバージョンをできるだけ増やすために、どんなフォームを設置すれば、ユーザーは気軽に問い合わせができるか?」について考えてみることが大切です。
問い合わせフォームがユーザーにとって極力ストレスがなく、楽な画面に設計し、できるだけ多くのユーザーからのコンタクトを獲得してビジネスの成果を上げることをゴールにしましょう。
顧客管理も重要
問い合わせフォームを長期間利用していると、過去に問い合わせをしてきた顧客データや、顧客からの意見(VOC=Voice of Cutstomer)が蓄積されていきます。
顧客データやVOCは、自社にとって商品・サービス改善の大きなヒントになり得る、貴重な財産です。それらは、日々のマーケティング活動に活かしていくこともできます。
例えば一度、顧客からの問い合わせアクションを獲得したあとに、さらにフォローメールをして顧客との関係を育む、すなわち、検討から成約に顧客ステータスを引き上げていく、といったアプローチもできます。
このような顧客へのアプローチを「CRM(Customer Relationship Management=顧客関係管理)」と呼び、近年、マーケティング分野で非常に重要な取り組みだと位置づけられています。
ただし、顧客の個人情報取得時に「今後、メルマガやDMを送ってもOKですか?」といった、顧客本人からの許諾(パーミッション)を必ず取る必要があります。本人の許諾無しに、一方的にセールスメールを送り付けることは違法に当たりますので、十分に気をつけて先々のアプローチを考えていきましょう。
問い合わせフォーム埋め込みでよくある用語
問い合わせフォームの埋め込みを行う際、理解しておくと作業がスムーズになる用語を解説します。
テキストボックス
フォーム内のテキスト入力欄です。問い合わせ内容など、ユーザーに自由記述してもらいたい場合に設置します。
プレースホルダテキスト
テキストボックスの中にある例文のことです。ユーザー入力時に、何を書けば良いのか迷わないように、イメージとなる例文を用意します。
ラジオボタン
ユーザーが、選択式の質問項目(単一選択、シングルアンサー)に回答するためのボタンです。
選択前が「〇」、選択後が「◉」などで表示されます。
ユーザー側も、自分が選んだ回答がひと目で分かります。
チェックボックス
ユーザーが、選択式の質問項目(複数回答、マルチアンサー)に回答するためのチェックマークです。
ユーザーが選択すると、四角いボタンの中にチェックマークがつきます。
プルダウン
選択項目をクリックすると、複数の選択肢が表示され、その中から1つを選ぶ回答形式です。
選択肢の数が多い場合に使います。
ラジオボタンやチェックボタンを並べると選択肢が多すぎて、フォーム全体が見にくくなってしまう際などに使うのがおすすめです。
レスポンシブ
スマホ・PC・タブレットなど、ユーザーの利用端末に合わせてデザイン・レイアウトを見やすいように切り替えて表示させることです。
昨今のユーザーはWebサイトを閲覧する際、スマホで見る割合が高くなっています。
スマホに最適なデザインで見せられるかどうかもフォーム設計時に重視する必要があります。
フォーム離脱率
入力フォームを閲覧したものの、入力・送信が完了せず、ページから離れたユーザーの割合のことです。
例えば、会員登録などをしようとして入力フォーム画面にたどり着いたものの、何かの理由で離脱してしまうユーザーは多く、全体の約7割程度にも上ると言われています。
フォーム離脱率が高い場合には、ユーザーの入力負担を下げるなど、改善が必要です。
埋め込み型フォーム
Webページの一部(ページの下部など)に入力フォームが埋め込んである状態を「埋め込み型フォーム」と呼びます。
別途、入力フォーム画面だけが独立した別ウインドウに移動する必要はありません。
ユーザーがランディングページなどを見て、その場でスムーズに問い合わせアクションに移ることができます。
CVR(コンバージョンレート)
CVR(コンバージョンレート、コンバージョン率)とは、ページ閲覧ユーザーの中から問い合わせアクションを完了したユーザーの割合を指します。
入力フォームの場合、CVRの平均値は、約30%程度(入力フォームにアクセスし、そこから問い合わせを完了するまでの割合)です。
EFO(エントリーフォーム最適化)
EFOとは「エントリーフォーム最適化」という意味です。
入力フォームが、より多くのユーザーにとって使いやすく、問い合わせアクションが完了しやすいものに改善する取り組みを指します。
入力フォームは「一度設置したら終わり」ではなく、実際に問い合わせが集まる状況を見ながら分析・最適化をしていく必要があります。
CTA(行動喚起)
CTAとは、ユーザーの行動を促すことです。
企業がユーザーに対して「こうして欲しい(例:問い合わせをしてほしい)」と思う行動を起こさせるのがCTAです。
多くの場合CTAとは、ボタンやリンクの形式でWebサイト上で表現されます。
より多くの問い合わせを獲得するためには、「お問い合わせはこちらから」などと表記したCTAボタンが目立ち、ユーザーにとって端的に分かりやすいものになるよう、さまざまな工夫をする必要があります。
reCAPTCHA(リキャプチャ)
reCAPTCHAはGoogleが提供しているサービスで、botと呼ばれる機械をはじくためのものです。
よくWebサイトのログイン画面などで見かける「私はロボットではありません」や「〇〇の画像を選択してください」といったものがreCAPTCHAです。
あまり時間を掛けず、無料で簡単にフォームを埋め込むには?
問い合わせフォームの埋め込みは、問い合わせ窓口が分かりやすく、いつでもできるようになる、といったユーザー側のメリットだけではありません。企業側も、集めたデータをマーケティングに活かせるなど、数々のメリットがあります。
特に、問い合わせフォームツールを導入すれば、メーラーでeメールをやり取りする手法には無い、数多くの高度な機能を利用できます。
「フォームの埋め込み作業自体にはあまり時間をかけず、簡単に無料で、今すぐ導入したい」と考えている方は、「formrun」をまずは無料で利用してみてください。