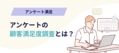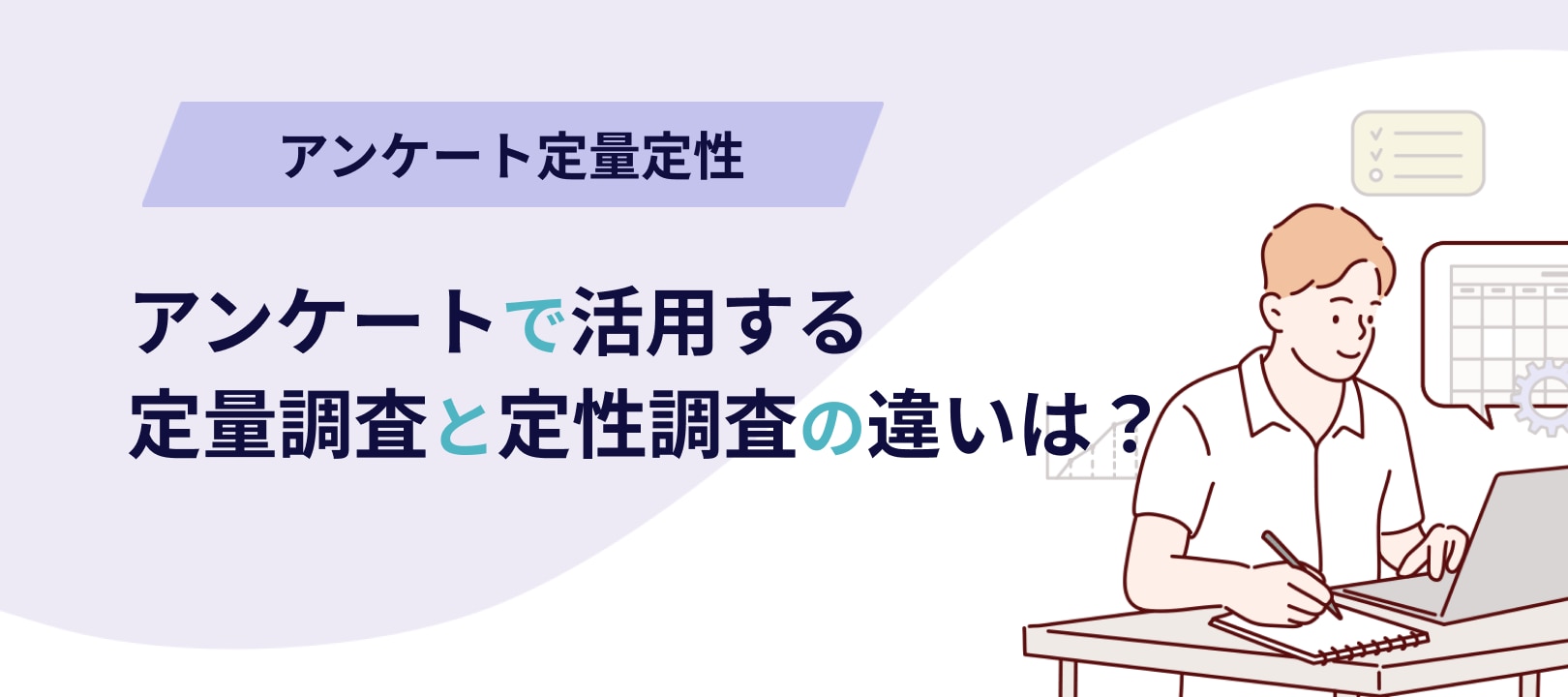
アンケートで活用する定量調査と定性調査の違いは?手法や使い分ける2つのポイントを解説
アンケートでは、定量調査と定性調査を用いて回答データを分析する場合があります。
それぞれの調査方法を適切に使い分けることで、必要な情報を正確に収集できるようになります。ただ、それぞれの違いや意味を理解していない方も少なくありません。
定量調査と定性調査を適切に使い分けるためには、しっかりと意味や活用目的、違いを理解しておくことが大切です。
本記事では、アンケートで活用する定量調査と定性調査の違いや手法、使い分けるポイントを解説します。
また、フォーム作成が簡単にできる「formrun」は、定量調査と定性調査のどちらもできることが特徴的です。
- プログラミング不要
- ワンクリックでrecaptcha設定可能
- マウス操作でデザイン設定可能
- 回答をリアルタイムで自動集計できる
- 自動メールやChatworkなどツール通知までついてる
- ここまでできて、基本料金無料
▼14日間有料プランの無料でトライアルお試しもできるので、ぜひ一度お試しください
目次[非表示]
アンケートで活用する定量調査とは?
 アンケートで活用する定量調査とは、数量や割合、人数などの数値化できるデータを収集・分析する調査手法のことです。
アンケートで活用する定量調査とは、数量や割合、人数などの数値化できるデータを収集・分析する調査手法のことです。
例えば、アンケートでは「はい/いいえ」などの選択式の項目の、それぞれの回答割合を把握する際に活用が可能です。また、主に、数百人規模の対象者に向けてアンケートを実施する際に実施されます。
マーケティングでは、顧客満足度調査やブランドイメージ調査などでも実施されることがあります。さらに、定量調査によって特定のテーマの全体の構造や傾向を可視化させることも可能です。
アンケートで活用する定性調査とは?
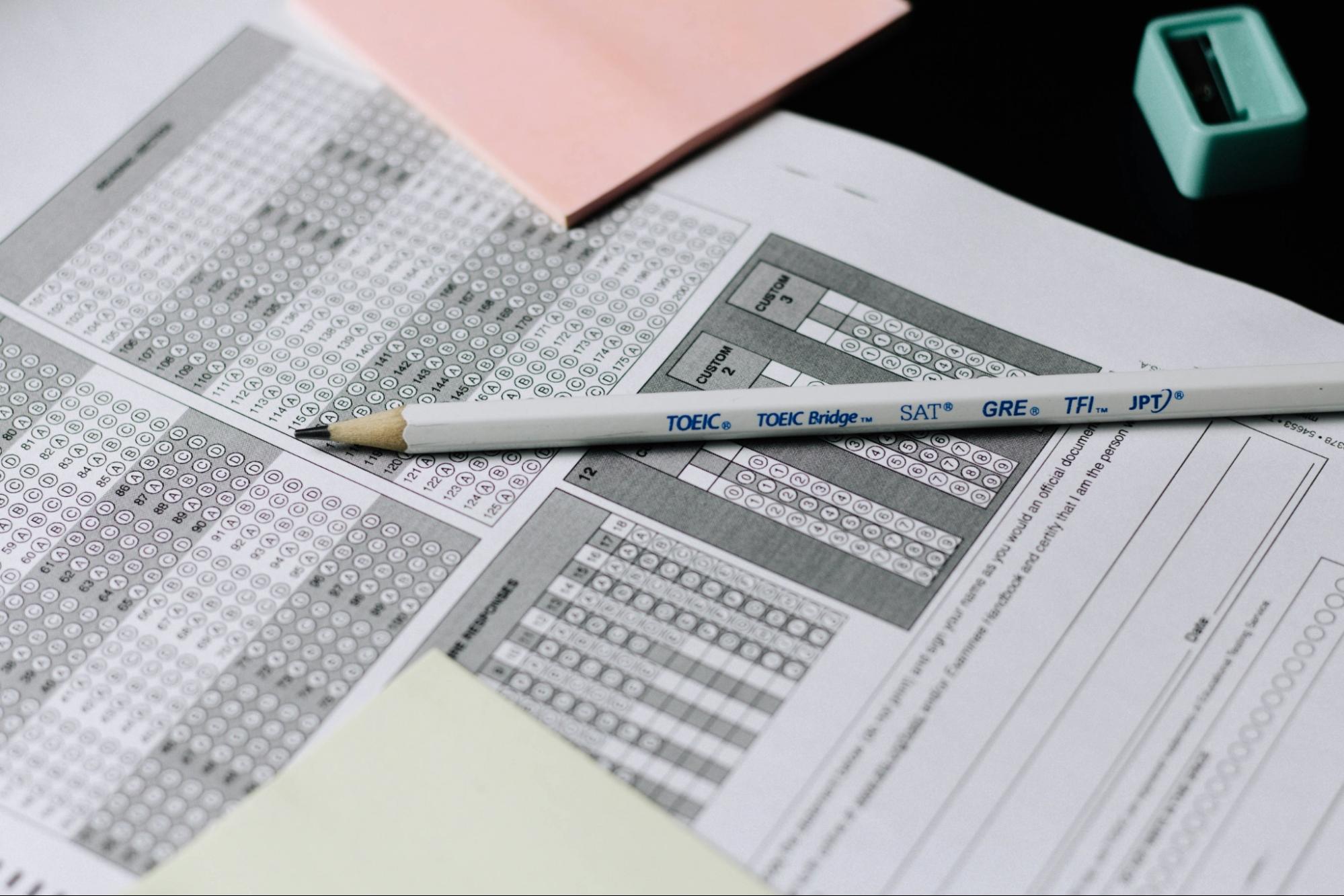
アンケートで活用する定性調査とは、行動や感情、価値観などの数値化できないデータを収集・分析する調査手法のことです。
例えば、アンケートでは自由回答形式の項目で、回答者の自由回答を深く読み解く際に活用されています。また、数人〜数十人ほどの規模のアンケートで、個人の回答の意図や行動原理を知る際に実施されます。
そのため、定量調査を実施すればアンケート回答の質を把握でき、回答だけでは把握できない想定外の意見も得ることが可能です。
定量調査と定性調査の主な3つの違い

アンケートで活用する定量調査と定性調査の主な3つの違いは、以下の通りです。
- 調査目的の違い
- 分析データの違い
- 調査手法の違い
ここでは、それぞれの違いを解説します。
調査目的の違い
定量調査は、主に仮説検証や実態把握・効果測定を目的に実施します。例えば、特定の商品は購入者のうち何人が高く評価し、何人が低く評価しているのかなどの調査で実施します。
一方で定性調査は、主に仮説立案や行動把握を目的に実施する手法です。例えば、個人の意見を参考に課題解決や新規サービスのアイデア・ヒントを発見するなどを目的に実施します。
そのため、定量調査と定性調査は、調査対象者の規模や収集・分析したい回答の種類が違います。
分析データの違い
定量調査では、数量や割合、人数などの数値化できるデータを収集・分析します。一方で定性調査では、行動や感情、価値観などの数値化できないデータを収集・分析します。
例えば、アンケートでの違いは、以下の通りです。
- 定量調査では選択式の項目を対象者に回答してもらう
- 定性調査では自由回答式の項目を対象者に回答してもらう
そのため、定量調査と定性調査を混同し間違ったデータの分析で活用してしまうと、正しくデータを調査できません。
調査手法の違い
定量調査の手法は、主に以下の通りです。
定量調査の調査手法 | 意味 |
|---|---|
インターネットリサーチ(Webアンケート) | インターネット上でアンケートを実施し調査する手法 |
会場調査(CLT) | イベントや調査会場にいる参加者にその場で調査する手法 |
ホームユーステスト(HUT) | 対象者の自宅に特定の商品を送り、実際に使った感想や評価を調査する手法 |
郵送調査・電話調査 | 郵送や電話を活用してアンケートを実施し調査する手法 |
定性調査の手法は、主に以下の通りです。
定性調査の調査手法 | 意味 |
|---|---|
グループインタビュー | 4〜8人ほどのグループを作り特定のテーマに関する話し合いをしてもらう手法 |
デプスインタビュー | 1対1の面談形式でインタビュアーが30〜90分ほどかけて対象者に調査する手法 |
エスノグラフィー(行動観察) | 対象者の自宅訪問や外出の動向を通して行動を観察する手法 |
ホームビジット(訪問調査) | 対象者の自宅で対象商品が使われている様子や環境を観察する手法 |
これから定量調査と定性調査を使い分ける際は、以上の手法とそれぞれの意味を理解しておくことが大切です。
定量調査と定性調査を使い分ける際の2つのポイント
 定量調査と定性調査を使い分ける際の2つのポイントは、以下の通りです。
定量調査と定性調査を使い分ける際の2つのポイントは、以下の通りです。
- 定性調査で仮説を立案し定量調査で検証する
- 定量調査で全体の傾向を把握し定性調査で深掘りする
ここでは、それぞれのポイントを解説します。
定性調査で仮説を立案し定量調査で検証する
最初に定性調査で仮説を立案し、定量調査で検証する方法で使い分けることが可能です。
例えば、消費者の理解を深めるために定性調査で仮説を立案し、定量調査で実際に検証するなどの方法があります。
定性調査だけでは分析や意見の裏付けに必要なデータ量が不足しているため、定量調査で補うことが大切です。また、定量調査を実施した結果、定性調査によって立案した仮説を裏付けられます。
つまり、定性調査では仮説立案、定量調査では仮説検証と使い分けられます。
定量調査で全体の傾向を把握し定性調査で深掘りする
反対に、定量調査で全体の傾向を把握し、定性調査で深掘りする方法で使い分けることもできます。
例えば、特定の商品・サービスの認知度を定量調査で把握し、商品・サービスの評価を定性調査で把握するなどが可能です。また、特定の商品・サービスの評価を定量調査で把握し、「なぜいいのか?」「なぜ悪いのか?」を定性調査で把握するなどもできます。
定量調査と定性調査は、目的に応じてどちらを先に実施した方が適しているのか検討した上で使い分けることが大切です。
定量調査を実施する3つのメリット
 定量調査を実施する3つのメリットは、以下の通りです。
定量調査を実施する3つのメリットは、以下の通りです。
- 客観的で説得力のあるデータを収集できる
- 数値化できるため可視化しやすい
- 大人数の協力が得やすくコストも抑えられる
ここでは、定量調査のそれぞれのメリットを解説します。
客観的で説得力のあるデータを収集できる
定量調査を実施するメリットは、客観的で説得力のあるデータを収集できることです。
定量調査は、収集したデータを数値として表すことができるため、誰が見てもわかりやすくなります。さらに、大規模な調査を実施してデータを数値化させるため、説得力も高くなります。
そのため、企業や事業の施策提案や意思決定の際に、根拠や裏付けとしての活用が可能です。また、裏付けとなるデータがあるため、仮説検証や需要予測、リスク対策などにも活用できるようになります。
数値化できるため可視化しやすい
数値化できることでデータが可視化しやすくなることも、定量調査を実施するメリットの1つです。
調査結果を数値化できるため、グラフや表を用いて視覚的に見やすい調査結果としてまとめられます。さらに、大規模な調査でも全体の構造や傾向が一目でわかるようになるため、調査結果の理解も深まりやすくなります。
その結果、調査関係者以外の組織やチーム全体などへの情報共有をする際にも、スムーズに内容を伝えて理解してもらうことが可能です。
大人数の協力が得やすくコストも抑えられる
定量調査は、インターネット上やイベント会場、郵送などを通して一斉に実施できます。
さらに、「はい/いいえ」などの簡単な選択式の項目に回答してもらうだけで完了するアンケートがほとんどです。特に、インターネットリサーチ(Webアンケート)を実施する場合、作成から収集まで気軽にできます。
そのため、数百人〜数千人規模のアンケートを実施する場合でも協力が得やすく、実施にかかる時間や費用、手間なども低くなります。
資金力があまり高くない企業や組織でも、気軽に実施できることは大きなメリットの1つです。
定量調査を実施する際の注意点

定量調査を実施するメリットは数多くありますが、反対に注意点もいくつか存在します。
特に、調査結果を数値化するため、数字を読み解く力やデータ分析の知識・スキルが必要です。データ分析やデータ活用の知識が不足していると、調査結果を十分に活用するのが難しくなります。
さらに、設置したアンケート項目以外の疑問や、特定の項目を深掘りした回答を得ることもできません。
そのため、定量調査を実施した後に定性調査を用いることなども検討しておくことが大切です。
定性調査を実施する3つのメリット
 定性調査を活用する3つのメリットは、以下の通りです。
定性調査を活用する3つのメリットは、以下の通りです。
- 深層心理や行動の背景まで調査できる
- 想定外の意見・回答を得ることができる
- 生の声や反応を確認できる
ここでは、定性調査のそれぞれのメリットを解説します。
深層心理や行動の背景まで調査できる
定性調査を実施するメリットは、深層心理や行動の背景まで調査できることです。
例えば、特定の質問をしたい際に「なぜそのよう回答したのか?」と、さらに深掘りができます。さらに、商品を高く評価した理由やリピートした理由まで調査できるため、行動の背景の把握も可能です。
そのため、消費者1人ひとりを深く理解できます。
特定の項目を深掘りしてただ結果のみを知るのではなく、その回答をした意図まで把握できることは大きなメリットの1つです。
想定外の意見・回答を得ることができる
想定外の意見・回答を得ることができることも、定性調査のメリットの1つです。
例えば、インタービューをしていく中で「そういえば」「ところで」などと質問に関連した意見を聞ける場合があります。
実際に対面して話し合うことで特定のテーマから会話が徐々に発展していき、最終的にニーズやアイデアまで知ることが可能です。
さまざまな意見・回答を特定の対象者から得られることは、定性調査ならではの魅力でもあります。
そのため、自社が想定しきれていない情報や意見を収集したい際には、活用してみることがおすすめです。
生の声や反応を確認できる
定性調査では、インタビューなどを通して直接意見を聞く機会があるため、生の声や反応を確認できます。
例えば、同じ回答でも回答した時の表情や目線、挙動によって発言の意図や意味合いが変わってきます。また、場合によっては回答が本心であるかどうかまで知ることが可能です。
同じ「よかった」の回答でも、笑顔で回答する場合と無表情で回答する場合では、大きな違いがあります。
これらの微妙な変化をとらえた上で、回答を収集するのは定性調査でしかできないため、本音や本心を聞き出したい場合は、定性調査を活用しましょう。
定性調査を実施する際の注意点

定性調査では、消費者の深層心理や行動の背景、本音などを聞き出すことができます。ただ、インタビュアーの質問力やコミュニケーション能力によって、回答者の回答も変化しやすくなります。
さらに、限られた時間の中でより多くの有益な情報を聞き出すためには、適切な対象者に対して適切な質問を行うことが大切です。
同じ対象者数で定性調査を実施した場合でも、対象者選定やインタビュースキルによって、結果が大きく変わることには注意が必要になります。
そのため、定性調査を実施する際は、インタビュースキルのある人材や適切な対象者選定を徹底しましょう。
定性調査の結果を定量調査で検証するならフォーム作成ツール「formrun」がおすすめ!

定性調査の結果を定量調査で検証できるフォーム作成ツール「formrun」の特徴は、主に以下の通りです。
- アンケート回答の集計も自動でできる
- 回答に応じて質問を出しわけできる
- 回答しやすいフォームが作成できる
ここでは、formrunの特徴をそれぞれ解説します。
アンケート回答の集計も自動でできる
formrun(フォームラン)では、回答がリアルタイムで集計されているため、いつでも回答結果が確認できます。
自動でデータをグラフ化、自動で回答データを一覧化できるので、簡単な集計・確認作業はformrunで完結します。
また、Googleスプレッドシートと連携したデータ集計やExcelファイルへのエクスポートも可能なので、より複雑な集計作業も可能です。
これまでアンケート回答状況の報告に集計の手間がかかっていた方は、ぜひformrunでアンケートフォームを作成し、集計作業まで効率化してみてください。
▼無料でお試しもできるので、ぜひ一度お試しください。
回答に応じて質問を出しわけできる
formrun(フォームラン)は質問数を最小限にしたまま顧客にあった質問に答えてもらうことが可能です。
フォーム作成において、フォームが長く見づらくなってしまうのはよくある悩みだとおもいます。
なるべく質問数を少なくし、回答者に合わせながら一貫した調査を行いたい場合は、
回答に合わせて必要な情報のみを表示することでフォームを短く、わかりやすくすることができる条件分岐を利用するのがおすすめです。
formrunでは無料で条件分岐を利用することが可能です。フォームが長くなってしまっている方、回答率が上がらない方はぜひformrunの条件分岐機能を利用してみてください。
▼クリックだけでフォームを作成するならformrun
回答しやすいフォームが作成できる
同じ回答選択肢の設問を繰り返す場合に利用できるマトリクス選択によって、アンケートを格段に見やすくすることが可能です。
回答者側:質問を人目で確認することができたり、一度に複数の質問に答えたりできるため、回答にかかる時間が大幅に短縮されます。
作成者:回答にかかる時間が短縮されるため回答率を上げるだけでなく、同じ尺度で複数の項目を評価することでデータの一貫性が保たれるので、データ解析が行いやすくなります。
アンケートに合わせたマトリクス形式を使った活用例などもあるのでぜひ利用してみてください。
▼ビジネスで使うなら「formrun」がおすすめ
定量調査と定性調査は目的に応じて適切に使い分けよう!

定量調査と定性調査は、名前が似ていることもあり混同しやすい言葉ですが、それぞれ意味が違います。
数値化できるデータを収集・分析できるのが定量調査で、数値化できないデータを収集・分析するのが訂正調査です。また、それぞれにメリットや注意点があり、活用方法や目的も大きく違います。
そのため、調査したいテーマや検証したい内容に応じて、適切に使い分けたり併用したりするようにしましょう。
適切に活用できれば、より精度の高いデータを収集し新規事業や品質改善などで活用しやすくなります。
また、フォーム作成が簡単にできる「formrun」は、定量調査と定性調査のどちらもできることが特徴的です。
- プログラミング不要
- ワンクリックでrecaptcha設定可能
- マウス操作でデザイン設定可能
- 回答をリアルタイムで自動集計できる
- 自動メールやChatworkなどツール通知までついてる
- ここまでできて、基本料金無料
▼無料でお試しもできるので、ぜひ一度お試しください