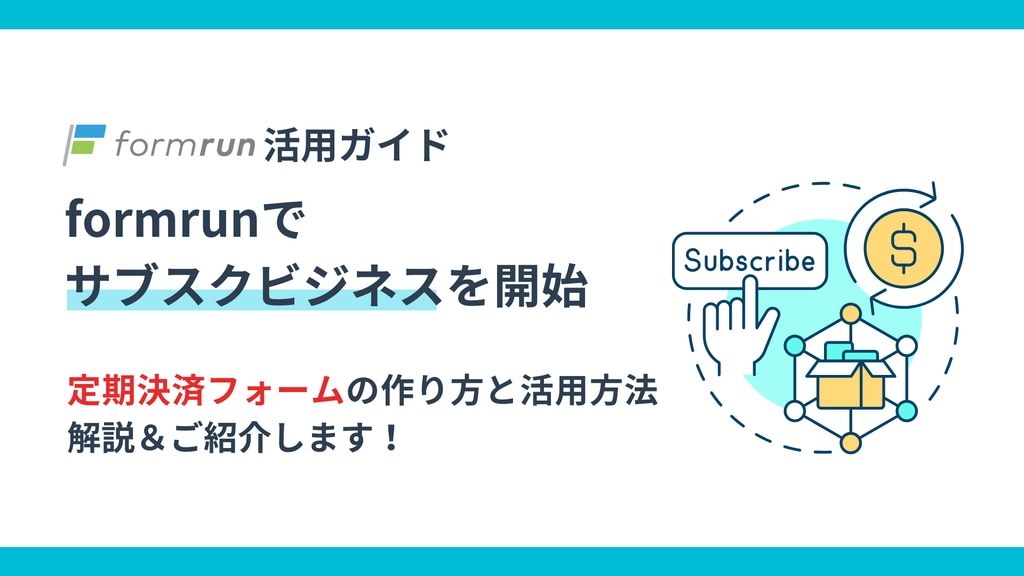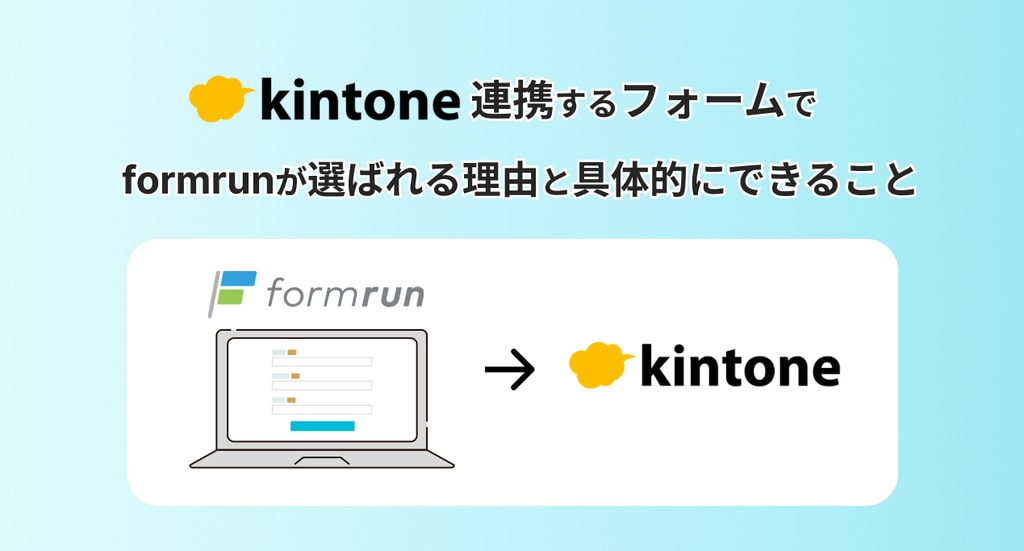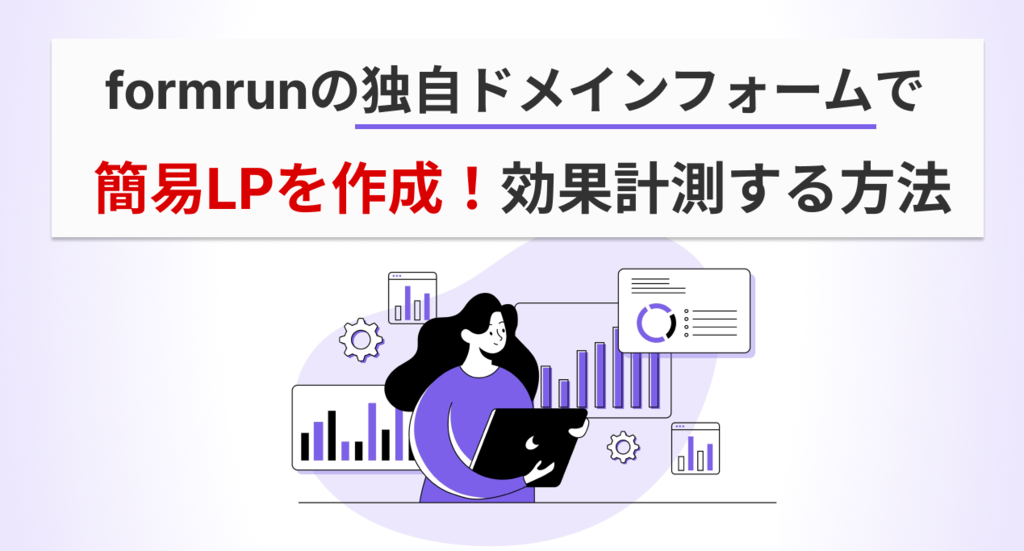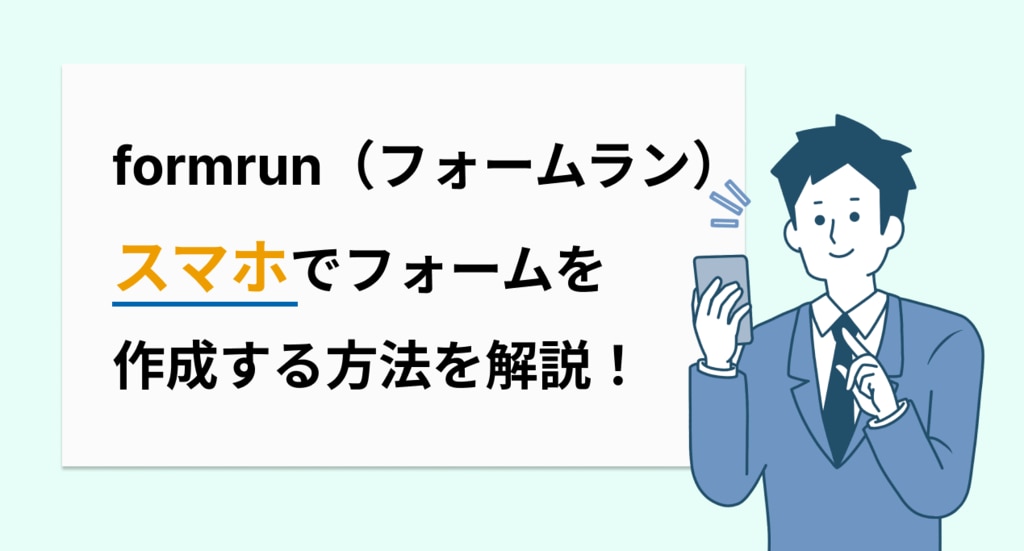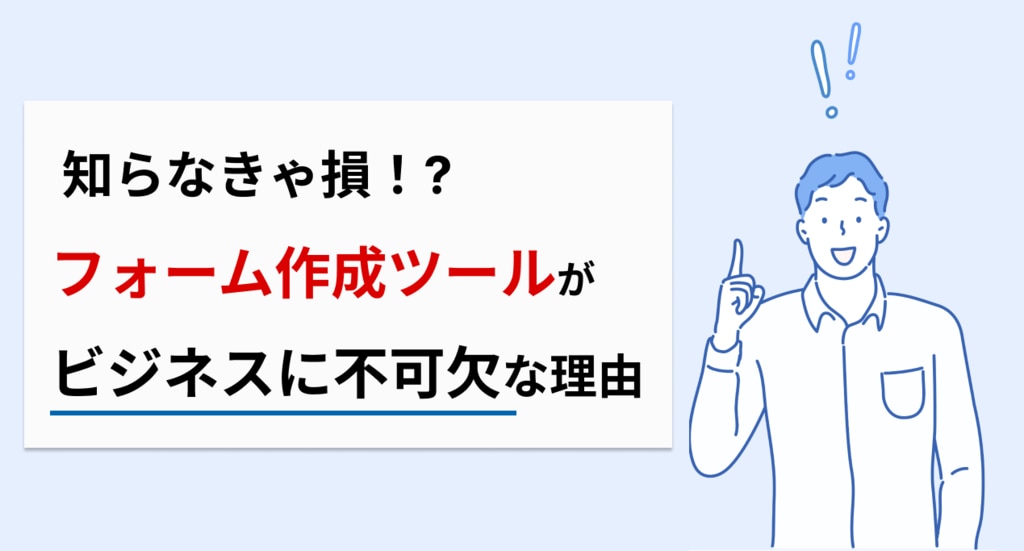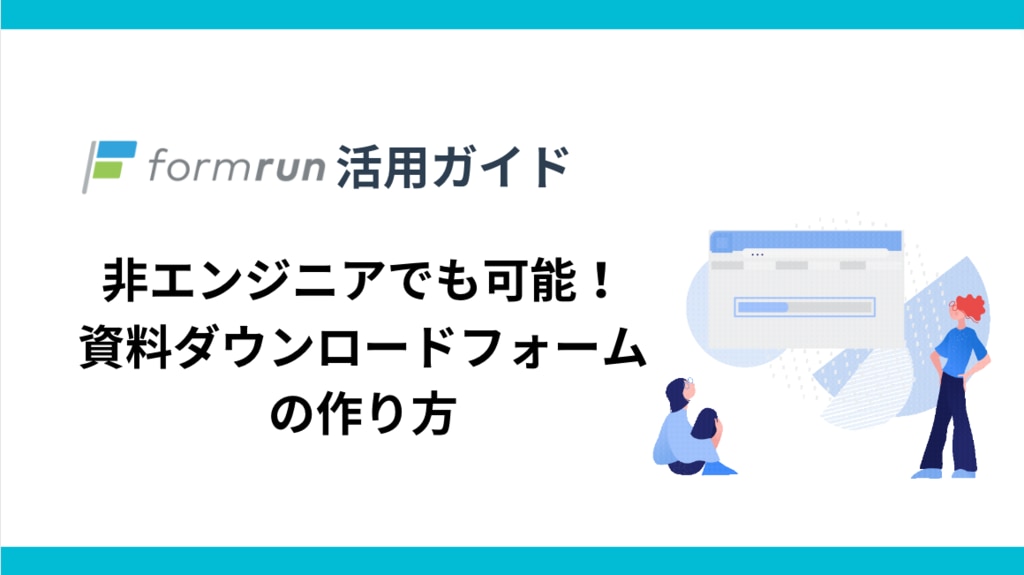アンケート調査の手法をプロが解説!進行手順や2つの作成ポイント・分析手法も紹介
「どのアンケート手法を使えばいいか分からない」
「目的に合わせてアンケート手法を選びたい」
このようなお悩みを持つマーケティング担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか?
アンケート調査は、顧客の声や市場の実態を把握し、サービス改善や意思決定に役立てるための有効な手段です。ただし、調査目的に合った手法を選ばなければ、得られるデータの精度や活用効果は大きく変わってしまいます。
本記事では、アンケート調査の代表的な手法8選や企業で活用される主なアンケートの種類、調査の進行手順、作成時の注意点、分析方法までをわかりやすく解説します。
目的に合わせて最適なアンケートフォームを作成するなら、フォーム作成ツール「formrun(フォームラン)」がおすすめです。
「formrun(フォームラン)」には、以下の特徴があります。
プログラミング不要
ワンクリックでrecaptcha設定可能
マウス操作でデザイン設定可能
回答をリアルタイムで自動集計
集計結果をExcelやスプレッドシートにエクスポートすることも可能
自動メールやChatworkなどツール通知までついている
ここまでできて、基本料金無料
目的に合ったアンケートを用意したい方は、ぜひ「formrun(フォームラン)」をお試しください。
目次[非表示]
アンケート調査とは?

アンケート調査とは、紙やインターネット上であらかじめ用意された統一的な設問に対して、対象者から回答を得ることで、意見や行動を把握するための調査手法です。
主に「はい・いいえ」や選択肢形式の数値化できるデータを収集する「定量調査」として活用され、得られた情報はマーケティング戦略やサービス改善など、企業や自治体の意思決定に役立てられます。
調査形式には大きく分けてオンライン(ネットリサーチ)とオフライン(紙アンケート、会場調査、郵送調査など)があり、目的や対象に応じて最適な手段を選ぶ必要があります。
アンケート調査を行う場合には、目的やターゲットに応じて手法を柔軟に選びましょう。
定量調査と定性調査の違い
 アンケート調査には「定量調査」と「定性調査」の2つの代表的な手法があります。
アンケート調査には「定量調査」と「定性調査」の2つの代表的な手法があります。
定量調査は、「はい・いいえ」や複数選択形式など、数値として集計できる回答を得るための手法です。ネットリサーチ、郵送調査、会場調査、訪問調査、街頭調査などが該当し、得られたデータのグラフ化や統計的な分析が行いやすい特徴があります。
一方、定性調査は、自由記述や対話形式を用いて個人の意見、感情、行動など数値化しにくい情報を掘り下げていく手法です。デプスインタビューやグループインタビュー、日記調査などが代表例で、潜在的なニーズや価値観の理解につながります。
調査目的に応じた手法を選ぶことが重要であり、たとえば顧客満足度の全体像を把握したい場合は定量調査を、サービス改善に向けた具体的な声を知りたい場合は定性調査を選ぶことがおすすめです。
アンケートの主な8つの調査手法
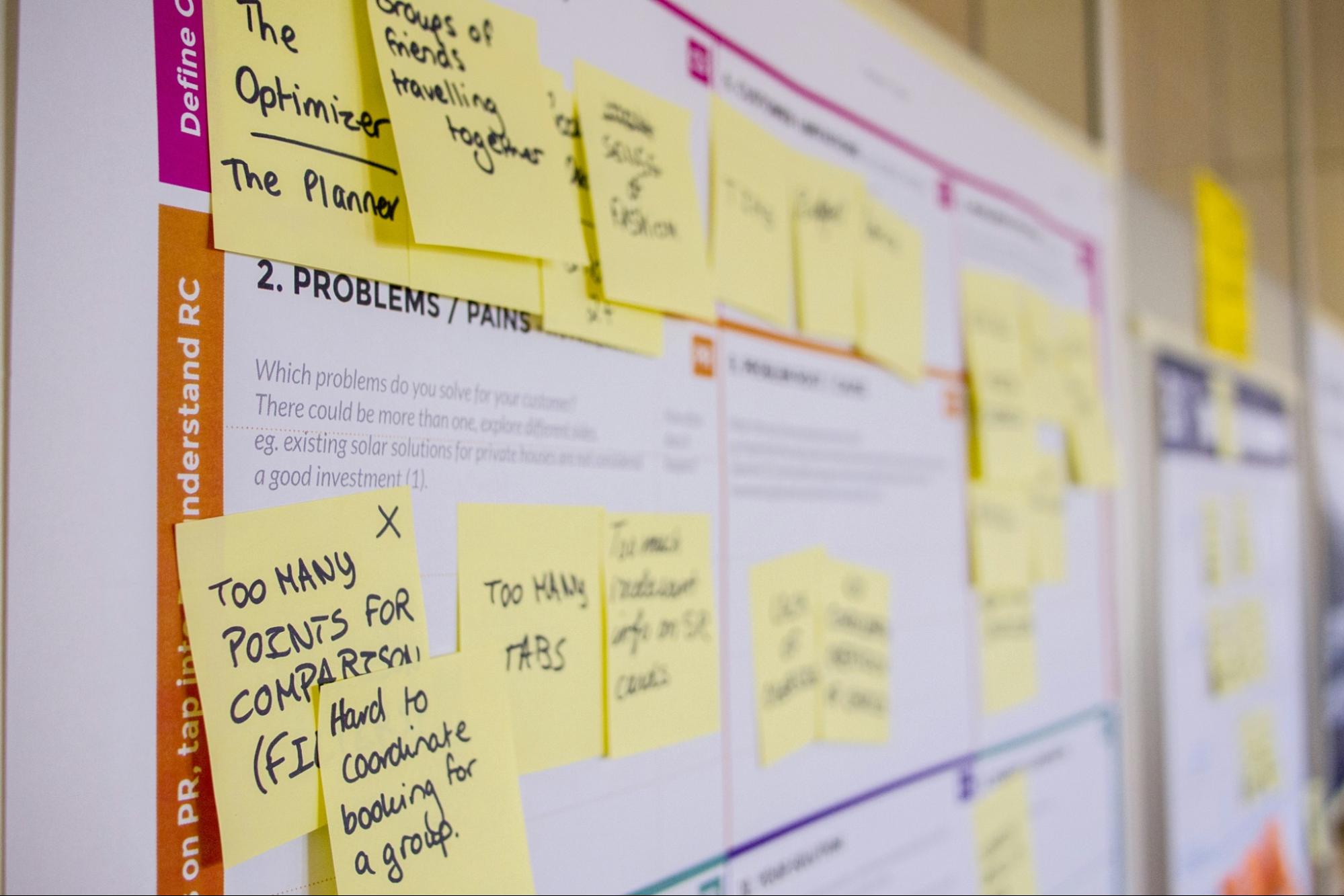
アンケート調査は、顧客の声や市場のニーズを把握するための重要な手段です。しかし、アンケートといっても、その実施方法にはさまざまな種類があります。
インターネット調査
郵送調査
街頭調査
会場調査
電話調査
覆面調査(ミステリーショッパー)
ホームユーステスト(HUT)
訪問留置調査
ここでは、アンケートの主な8つの調査手法を詳しく解説します。
インターネット調査
インターネット調査は、コストを抑えながら短期間で多くの対象者に一斉にアプローチできる効率的な手法です。
アンケートフォームの作成から、回答の回収、集計までをすべてオンライン上で完結できるため、作業の手間が少なく済みます。また、匿名性が高いため、回答者の本音を引き出しやすいメリットもあります。
さらに、QRコードを活用することで、実店舗などでも簡単に顧客調査を行うことが可能です。ただし、高齢者のモニターを獲得することが難しく、回答の質にばらつきが出る場合があります。
郵送調査
郵送調査は、紙のアンケート用紙を対象者に郵送し、記入後に返送してもらう手法です。
高齢者を含む幅広い世代に対応できる点が特徴で、インターネットに不慣れな層からも回答を得やすくなっています。回答者が自分の都合に合わせてゆっくりと記入できるため、比較的丁寧な回答を得られる傾向があります。
ただし、調査用紙の発送や回収に時間がかかるため、即時性に欠ける点には注意が必要です。また、若年層の回答率が低くなる傾向があるため、サンプルの偏りにも注意しましょう。
街頭調査
街頭調査は、駅前や繁華街など人通りの多い場所で通行人に直接声をかけ、アンケートを実施する方法です。
対面でのやり取りを通じて、信頼性の高いリアルな意見を得られる点が魅力です。地域特有の事情や現地のニーズを把握する調査にも適しており、臨場感のあるデータが収集できます。
ただし、調査対象者が条件に合っているかを判断するためのスクリーニングが必要となり、調査員の声かけスキルや対応力に結果が左右される点には注意が必要です。
会場調査
会場調査は、特定の会場に対象者を招いて行う形式で、製品の試用やパッケージの評価など、体験を通じてデータを収集する方法です。
調査員がその場で回答状況を確認し、不明点をフォローできるため、精度の高いデータを得られるのが特徴です。実際に商品を使用してもらうことで、詳細な意見や感想を集めやすくなります。
ただし、モニターの交通費や会場の運営費など、全体のコストは高くなる傾向にあり、外出が難しい対象者への対応は難しくなります。
電話調査
電話調査は、調査員が対象者に直接電話をかけ、口頭でアンケートを実施する手法です。
その場で質問内容を説明したり、補足を加えたりできるため、理解度を高めたうえでの回答を得ることが可能です。また、対話形式であることから柔軟に意見を聞き出せるため、定性的な情報を収集したい場合にも適しています。
一方で、電話に出てもらえなかったり、話を途中で切られたりする可能性があるため、導入前に調査趣旨を丁寧に伝えることが重要です。
覆面調査(ミステリーショッパー)
覆面調査は、調査員が一般の顧客を装って店舗や施設を利用し、実際のサービス状況を評価する手法です。
接客態度や清掃状況など、現場での実態をありのままに把握できます。事前に評価基準や調査項目を決めておくことで、複数の店舗間で比較しやすい標準化されたデータを収集できます。また、コールセンターなど非対面のサービスにも応用が可能です。
ただし、実施にかかるコストが比較的高く、調査員を確保することにも手間がかかる点が課題です。
ホームユーステスト(HUT)
ホームユーステストは、製品を調査対象者の自宅に送付し、一定期間使用してもらった後に評価を得る手法です。
生活環境の中で製品を試してもらうことで、実使用に即したリアルな意見を集められます。同居する家族からのフィードバックも得られるため、複数視点での評価が可能です。
ただし、製品の配送や安全性・機密性への配慮が求められ、コストや管理面での負担が大きくなります。最近では、Webアンケートと組み合わせて効率的にデータを回収するケースも増えています。
訪問留置調査
訪問留置調査は、調査員が家庭を訪問してアンケート用紙を手渡し、後日回収する方式の調査です。
モニター登録がされていない層や、特定エリアに住む住民を対象とした調査に適しています。調査員が直接訪問するため、信頼性の高いデータを得やすく、個別のフォローアップも可能です。
しかし、大規模な調査には向かず、多くの時間と人手を必要とするため、コスト面やリソース確保の課題があります。地域密着型の詳細な情報収集を目的とする場合に有効な手法です。
企業が行う代表的なアンケート調査の種類【テンプレート付き】
 企業が実施するアンケート調査は、顧客や従業員、商品・サービス、広告、ブランドなどのさまざまな対象に対して行われます。それぞれの調査は目的や対象が異なるため、最適な設計と手法が重要です。
企業が実施するアンケート調査は、顧客や従業員、商品・サービス、広告、ブランドなどのさまざまな対象に対して行われます。それぞれの調査は目的や対象が異なるため、最適な設計と手法が重要です。
顧客満足度調査
従業員満足度調査
商品・サービス調査
広告効果測定調査
ブランド・認知度調査
ここでは、企業が行う代表的なアンケート調査をテンプレート付きで解説します。
顧客満足度調査
顧客満足度調査は、自社の商品やサービスを利用した顧客に対して、その満足度やリピート意向を把握することを目的とした調査です。
顧客満足度の向上は、売上の拡大や企業イメージの向上に直結するため、多くの企業が重視しています。特にSNSなどで顧客の評価が拡散されやすい現代では、顧客の声をリアルタイムで把握することが施策の即時改善に役立ちます。
調査にはネットリサーチが主に用いられ、短期間で多くのデータを収集できる点が魅力です。顧客が期待を超えた体験をしているかを把握するためにも、有効な調査手法です。
従業員満足度調査
従業員満足度調査は、従業員を対象に職場環境や組織運営、上司・同僚への評価などを行う調査です。
調査の目的は、働きやすい職場づくりのための課題発見や人事制度の見直し、さらには離職防止などです。特にネットリサーチ形式で行えば、匿名性が確保され、従業員の本音を引き出しやすくなります。
満足度が高い職場は生産性が上がるだけでなく、従業員の定着率やエンゲージメント向上にもつながります。調査結果を通じて、経営層と現場との意識ギャップを可視化できる点も大きなメリットです。
商品・サービス調査
商品・サービス調査は、自社が提供する商品やサービスの実際の使用実態や満足度、改善点を明らかにするために行う調査です。
特にホームユーステストでは、対象者に実際に商品を試してもらい、リアルな評価を収集できます。このような調査は、商品開発や改良、さらには新製品のアイデア出しにも役立ちます。
また、コンセプトが消費者に正しく伝わっているかどうかを確認する目的でも重要です。実際に使用したうえでの具体的な意見を集められる点が、他の調査と比較した際の大きな特徴です。
広告効果測定調査
広告効果測定調査は、テレビCMやWeb広告などの認知や印象、行動喚起の効果を可視化するために行われる調査です。
広告そのものと商品・サービスの両方に関する評価を得ることにより、広告施策の妥当性を検証できます。主な評価指標には、広告の認知率、記憶率、購買意欲の変化などがあります。
Web調査を用いることで、短期かつ低コストで大規模なデータ収集が可能です。広告の改善点の洗い出しや、次回のクリエイティブ戦略への示唆も得られることから、広告効果を最大化するためにも重要です。
ブランド・認知度調査
ブランド・認知度調査は、自社のブランドが市場でどの程度認知されているか、どのようなイメージを持たれているかを明らかにする調査です。
競合他社との比較により、自社ブランドの強みや弱みを把握できます。この調査を定期的に行うことで、市場の変化やブランド戦略の成果を継続的に評価し、必要な見直しが可能です。
調査にはWeb調査が主に活用されており、広い年代や地域へアプローチできます。ブランド戦略や広告施策の方向性を定めるうえで、欠かせない情報源です。
アンケート調査の進行手順【6STEP】
 アンケート調査は、マーケティング課題の把握から施策への反映までを一貫して行うことで、成果につながる情報を得られます。
アンケート調査は、マーケティング課題の把握から施策への反映までを一貫して行うことで、成果につながる情報を得られます。
マーケティング課題・目的の整理
アンケートの選定・調査の企画
調査票・アンケートの作成
アンケートの実施・回答回収
アンケートの集計・分析
フィードバックと施策への活用
ここでは、効果の高いアンケート調査を行うための6つのステップを紹介します。
1.マーケティング課題・目的の整理
まず、マーケティング上の課題や目的を明確にしましょう。
施策が思うような成果を出していない場合、その原因が「リーチ」「ターゲティング」「行動喚起」のどこにあるのかを整理する必要があります。
アンケートは「何となく」で実施するのではなく、課題を検証したいのか、それとも解決策の有効性を確認したいのか、目的をはっきりと定めてから取り組むことが重要です。
目的が曖昧なまま調査を行うと、得られたデータが実務に結びつかず、貴重なリソースを無駄にしてしまう可能性があります。
2.アンケートの選定・調査の企画
調査目的が明確になったら、目的に沿って必要な情報や集計手法を企画段階で設計しましょう。
収集すべきデータ項目、分析方法、そしてどのような対象者に対して調査を行うかを決定します。調査の実施方法もここで選び、インターネット調査、会場調査、訪問調査などから手段を選びましょう。
また、定量調査と定性調査の違いも把握しておくことが重要です。前者は数値的な傾向を把握するのに適し、後者は具体的な意見の背景や理由を深く知るのに役立ちます。
3.調査票・アンケートの作成
調査票の設計段階では、調査目的を踏まえて、必要な情報を効率よく得られるように設問内容と順序を決めましょう。
質問文は簡潔かつ明瞭にし、長すぎたり曖昧だったりする表現は避けることをおすすめします。また、「ダブルバーレル(二重質問)」や「二重否定」など、回答者が混乱しやすい表現は使用しないようにしましょう。
ただし、性別や年齢などの属性情報は、分析の際に重要な軸となるため、必ず取得しておくことをおすすめします。信頼性のあるデータを得るには、サンプルサイズの設定も欠かせません。特定の回答に誘導しない中立的な設問設計を意識しましょう。
4.アンケートの実施・回答回収
調査票が完成したら、実際にアンケートを実施・配布に移りましょう。
アンケートフォームとして実装し、インターネット、郵送、訪問、街頭など、調査目的に合った手段で配布を行います。回答者にはアンケートの目的や意図を事前に伝え、理解と納得のもとで協力を得ることが大切です。
また、回収した回答内容はミスや未記入がないか確認し、データの質を確保します。回収の過程で、アンケートの印象や改善点に関して意見を聞けると、次回以降の調査品質の向上につながります。
5.アンケートの集計・分析
回収したデータは、まず単純集計(GT表)で全体の傾向を把握し、属性別に分析しましょう。
クロス集計では、サンプル数が少ないと信頼性が下がるため、最低でも30以上を目安とします。より高度な分析が求められる場合は、GAP分析やコレスポンデンス分析、因子分析、クラスター分析などの統計手法を検討しましょう。
また、定量調査の結果はグラフ化することで、傾向を視覚的にとらえやすくなり、社内での共有やプレゼンテーションにも役立ちます。仮説との一致や不一致を確認し、そこからインサイトを導き出すことが重要です。
6.フィードバックと施策への活用
分析結果が得られたら、結果をもとにマーケティング課題に対する仮説の検証を行いましょう。
得られたデータや気付きを記録し、今後の施策立案や改善策に反映させることが重要です。また、調査目的がどれだけ達成できたかを評価し、社内関係者と結果を共有することで共通認識を持てます。
アンケート実施前から社内で活用方法をすり合わせておけば、調査後の行動に迷いが生じにくくなります。アンケート結果は、次の意思決定で信頼性の高い資料として活用しましょう。
アンケート作成時に注意すべき2つのポイント
 効果の高いアンケートを実施するためには、単に質問を並べるだけでは不十分です。設問の設計や調査対象の設定が不適切だと、正確なデータが得られず、分析や施策立案に支障が出てしまいます。
効果の高いアンケートを実施するためには、単に質問を並べるだけでは不十分です。設問の設計や調査対象の設定が不適切だと、正確なデータが得られず、分析や施策立案に支障が出てしまいます。
回答者の負担になる要素を極力排除する
目的に合わせて必要な属性・サンプルサイズを事前に設定する
ここでは、アンケート作成時に注意すべき2つの重要なポイントを解説します。
回答者の負担になる要素を極力排除する
アンケート作成時には、回答者がストレスなく答えられるように配慮することが重要です。
設問が長すぎたり、構成が複雑すぎたりすると、回答の途中で離脱してしまう可能性が高まります。そのため、質問文は簡潔にまとめ、ひと目で内容が理解できるように心がけましょう。
また、誘導的な設問や、回答の初期段階から考えさせるような難解な内容は避けるべきです。こうした設問は回答意欲を損ない、正確なデータの収集を妨げる原因になります。
さらに、必要に応じて画像や図表を活用し、視覚的な補助を加えることで、質問内容の理解をサポートできます。質問数の目安は10〜20問程度とし、調査の目的や内容に応じて調整することが大切です。
目的に合わせて必要な属性・サンプルサイズを事前に設定する
アンケートの精度を高めるには、対象とする属性情報とサンプルサイズの設定が不可欠です。
性別・年齢・職業などの属性データは、分析の軸となり、得られた結果の妥当性や再現性を担保する重要な要素です。属性データが不足すると、特定層の偏りに気付けず、正確な仮説検証が困難になります。
また、回答数が少なすぎると統計的な信頼性が低下し、データとしての有効性が薄れてしまいます。特に傾向分析を行う場合には、ある程度のサンプル数が必要です。
調査目的や分析方法に応じて、必要なサンプルサイズを事前に計算し、十分な数の回答を確保しましょう。定量調査であれば、最低でも30件以上のサンプルが必要なため、それ以上の件数を目標とすることおすすめです。
アンケート調査の分析を行うための代表的な3つの集計手法
 アンケート調査を分析する際には、回答内容を整理・可視化するための集計手法が欠かせません。それぞれの手法には役割や適した分析対象があり、目的や設問形式に応じて使い分けることが重要です。
アンケート調査を分析する際には、回答内容を整理・可視化するための集計手法が欠かせません。それぞれの手法には役割や適した分析対象があり、目的や設問形式に応じて使い分けることが重要です。
単純集計
クロス集計
フリーテキスト集計
ここでは、アンケート調査の分析を行うための代表的な3つの集計手法を解説します。
単純集計
単純集計は、アンケートの各設問に対して、回答数や割合を集計し、全体の傾向を把握するための基本的な分析手法です。
この手法では、5段階評価やYes/Noなど単一の質問項目に対して、平均値や比率を算出します。これにより、全体としてどのような回答傾向があるのかを簡潔に確認できます。
集計結果はGT表(Grand Total)と呼ばれる表形式で表され、設問ごとの分布が一覧で見やすく整理しましょう。クロス集計や詳細分析を行う際にも活用できます。
クロス集計
クロス集計は、2つ以上の質問項目をかけ合わせることで、属性ごとの傾向や関連性を明らかにする分析手法です。
例えば、性別と満足度、年代と購買意欲などを組み合わせ、各層の回答傾向を比較できます。表側(縦軸)と表頭(横軸)に異なる項目を設定し、どの属性にどのような傾向があるのかを可視化します。
この手法を効果的に活用するには、事前に仮説や分析目的を明確にしておくことが重要です。無目的に多用すると、分析効率が低下するだけでなく、誤解を招く可能性もあります。また、一定の信頼性を確保するために、クロス集計には最低30サンプル以上のデータ数を集めましょう。
フリーテキスト集計
フリーテキスト集計は、自由記述形式で得られた回答内容を分析する手法です。
評価の高い意見やネガティブなコメントとその回答者属性を照らし合わせ、傾向や課題を把握します。
まずは回答を一覧化し、アフターコーディングによってキーワードやカテゴリに分類することで、定量的な集計が可能です。さらに、頻出語を分析したり、ワードクラウドを活用したりすることで、主要な意見やテーマを視覚的に理解できます。
最近ではテキストマイニングや生成AIを用いて、単なる単語の出現だけでなく、文脈や感情をとらえた深い分析も可能になってきています。特に顧客の本音を把握したい場面で有効な手法です。
アンケートの手法に適したフォーム作成ツールなら「formrun」がおすすめ!
 formrunにはアンケートに対応している以下の特徴があります。formrunを利用するメリットは下記の3点です。
formrunにはアンケートに対応している以下の特徴があります。formrunを利用するメリットは下記の3点です。
アンケートテンプレートが豊富
EFO(フォーム最適化)で回答者の離脱を防げる
アンケート回答の集計も自動でできる
アンケートテンプレートが豊富
formrun(フォームラン)は、120種類以上のテンプレートが用意されています。
アンケートフォームで使えるテンプレートは16種類あり、主に顧客アンケート、イベント・セミナーアンケート、社内アンケートなど用途に合わせたテンプレートが選べます。
formrunのテンプレートはそのまま利用できるリッチな見た目で、用途に合わせて必要な設問が最適な順番で配置されているため、設問タイトルを少し修正するだけで簡単に高クオリティのフォームを作成可能です。
テンプレートの設問に項目の追加・削除・順番の変更などもワンクリックで簡単に修正できます。
ぜひformrunのテンプレートを使用して高クオリティなアンケートフォームを作成してみてください。
EFO(フォーム最適化)で回答者の離脱を防げる
送信する際のエラーや、項目数が表示されていない、ブラウザを間違えて閉じてしまうなど、フォームにまつわるよくある上記のようなストレスが原因でフォームから離脱するユーザーは7割を超えると言われています。
それらの離脱を防ぐため、回答者が便利にフォームを利用できる取り組みとして、残項目数表示や、ページ分割機能、入力途中保存、リアルタイムでのエラー表示機能などがあります。
そのためユーザーは、「自分の入力内容に間違いがないか」「あと何分で完了するか」などを常に把握できるため、回答負担が大幅に減ります。
EFO機能を導入するには約30,000円の費用がかかることが一般的ですが、formrunでは、わずか3,000円〜EFO機能を導入できます。ぜひformrunでEFO機能を導入し、フォームの通過率が上がる経験をしてみてください。
アンケート回答の集計も自動でできる
formrun(フォームラン)では、回答がリアルタイムで集計されているため、いつでも回答結果が確認できます。
自動でデータをグラフ化、自動で回答データを一覧化できるので、簡単な集計・確認作業はformrunで完結します。
また、Googleスプレッドシートと連携したデータ集計やExcelファイルへのエクスポートも可能なので、より複雑な集計作業も可能です。
これまでアンケート回答状況の報告に集計の手間がかかっていた方は、ぜひformrunでアンケートフォームを作成し、集計作業まで効率化してみてください。
目的に合わせて最適なアンケート手法を選択しよう!
 本記事では、アンケート調査の基本的な手法や進行手順、作成時の注意点、分析方法、企業が活用する代表的な調査例を詳しく紹介しました。
本記事では、アンケート調査の基本的な手法や進行手順、作成時の注意点、分析方法、企業が活用する代表的な調査例を詳しく紹介しました。
アンケートは、顧客や従業員の声を可視化し、マーケティング施策やサービス改善に活用するための重要な要素であり、その設計や分析方法を最適化することで、意思決定の精度向上や顧客満足度の向上が期待できます。
目的に合ったアンケート手法を選定し、適切な調査設計と高品質なフォームを導入することで、データの活用価値を最大化し、ビジネス成果の向上につなげましょう。
目的に合わせて最適なアンケートフォームを作成するなら、フォーム作成ツール「formrun(フォームラン)」がおすすめです。
「formrun(フォームラン)」には、以下の特徴があります。
プログラミング不要
ワンクリックでrecaptcha設定可能
マウス操作でデザイン設定可能
回答をリアルタイムで自動集計
集計結果をExcelやスプレッドシートにエクスポートすることも可能
回答結果をリアルタイムで自動集計
自動メールやChatworkなどツール通知までついている
ここまでできて、基本料金無料
目的に合ったアンケートを用意したい方は、ぜひ「formrun(フォームラン)」をお試しください。